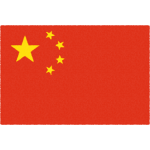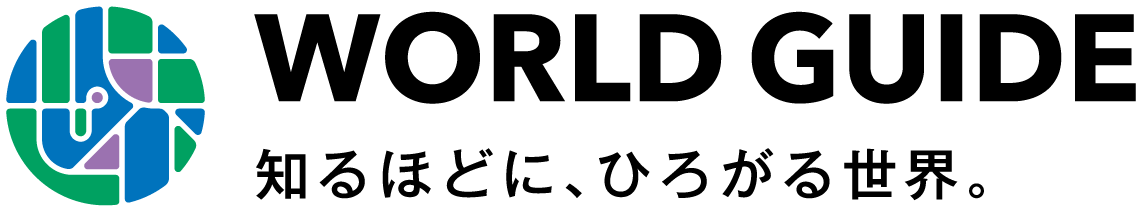国際連合食糧農業機関(FAO)の調査によると、リトアニアのヤギ飼養頭数は、1992年にわずか6,300頭という小規模な規模から1999年には23,700頭、最も高い値を示した2004年には27,205頭に達しました。しかしそれ以降、減少が目立つようになり、2013年には一時的に13,598頭まで落ち込みました。その後、2022年には14,990頭まで回復の兆しを見せていますが、依然として1990年代後半から2000年代初頭の数値を大きく下回っています。
リトアニア共和国のヤギ飼養頭数の推移【1961年~2023年】世界ランキング・統計データ
| 年度 | 飼養頭数(頭) | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 13,980 |
-6.74% ↓
|
|
| 2022年 | 14,990 |
1.97% ↑
|
|
| 2021年 | 14,700 | - | |
| 2020年 | 14,700 |
-2.65% ↓
|
|
| 2019年 | 15,100 |
5.59% ↑
|
|
| 2018年 | 14,300 |
6.64% ↑
|
|
| 2017年 | 13,409 |
-0.87% ↓
|
|
| 2016年 | 13,526 |
4.12% ↑
|
|
| 2015年 | 12,991 |
-6.08% ↓
|
|
| 2014年 | 13,832 |
1.72% ↑
|
|
| 2013年 | 13,598 |
-9.35% ↓
|
|
| 2012年 | 15,000 |
-6.25% ↓
|
|
| 2011年 | 16,000 |
8.84% ↑
|
|
| 2010年 | 14,700 |
-11.45% ↓
|
|
| 2009年 | 16,600 |
-15.74% ↓
|
|
| 2008年 | 19,700 |
-5.29% ↓
|
|
| 2007年 | 20,800 |
-5.39% ↓
|
|
| 2006年 | 21,984 |
-18.29% ↓
|
|
| 2005年 | 26,904 |
-1.11% ↓
|
|
| 2004年 | 27,205 |
23.85% ↑
|
|
| 2003年 | 21,966 |
-7.32% ↓
|
|
| 2002年 | 23,700 |
3.04% ↑
|
|
| 2001年 | 23,000 |
-6.88% ↓
|
|
| 2000年 | 24,700 |
4.22% ↑
|
|
| 1999年 | 23,700 |
28.11% ↑
|
|
| 1998年 | 18,500 |
9.47% ↑
|
|
| 1997年 | 16,900 |
15.75% ↑
|
|
| 1996年 | 14,600 |
17.74% ↑
|
|
| 1995年 | 12,400 |
19.23% ↑
|
|
| 1994年 | 10,400 |
24.61% ↑
|
|
| 1993年 | 8,346 |
32.48% ↑
|
|
| 1992年 | 6,300 | - | |
| + すべての年度を見る | |||
リトアニアのヤギ飼養頭数は、1992年から始まり、2004年にかけて急激に増加しました。この期間の成長はリトアニアの畜産業が多様化したことや、ヤギ乳や乳製品が地域市場での需要を高めたことが主な要因と考えられます。特に、1990年代初頭はリトアニアが旧ソ連から独立した直後であり、農業改革が活発に進められた時期でもあります。その中でヤギ飼養は、家畜業の新しい可能性として注目されました。また、初期の飼養頭数の増加に伴い、ヤギ関連産業への投資も拡大しました。
一方で、2004年以降は減少傾向が目立つようになります。この下降は、リトアニアのEU加盟(2004年)と関連があるとみられます。EU加盟後、農業補助金制度が変更され、同時に生産効率や環境規制が強化されました。これにより、一部の小規模農家がヤギの飼育を放棄した可能性があります。さらに、旧ソ連時代から続く畜産管理体制の移行過程で、小規模家畜の需要が徐々に下がり、農業機械化や集約化の進展がヤギ生産にも影響を与えたと推定されます。また、家畜飼育に必要とされる飼料や資源価格の上昇、若年層の都市部への移住といった社会的要因も影響を及ぼしたと考えられます。
近年では、2018年以降に若干の回復が見られるものの、過去のピーク時には及びません。これは、欧州全般で見られる「小規模な牧畜業の復権」を受けた動きや、ヤギ乳製品が再び注目を集めている影響と見ることができます。また、健康食品志向の高まりによるヤギ乳やチーズの需要拡大が、リトアニアの市場でも反映されている可能性があります。
リトアニアのヤギ飼養には、いくつかの課題が存在します。その一つは、農家の収益性を確保しつつ、伝統的なヤギ飼養の利点を維持するための包括的な政策不足です。特に若い農業従事者の減少や都市化の進行は、小規模なヤギ農家が直面する重要な問題として挙げられます。また、気候変動や地政学的な影響が、飼育環境や農業リソースの供給に影響を及ぼしています。例えば、ウクライナ紛争により飼料やエネルギー価格が急騰した状況は、農業におけるコスト圧力を強めています。
以上を踏まえ、将来的なヤギ生産の持続可能性を考えるためには、農村部の生産基盤を維持する政策策定が必要です。これには、EUが提供する補助金や技術支援を活用し、特に若い世代の農民を支援することが重要です。また、リトアニア国内外でのヤギ乳製品のマーケティング強化や輸出促進を通じて、農家の収益性向上を目指す取り組みが求められます。さらに、気候変動に適応した飼育環境整備や農業技術の導入による効率化にも注力すべきです。
結論として、リトアニアのヤギ飼養はかつてのピーク時からは縮小していますが、適切な対策を講じることで、再び新たな成長の可能性を切り開くことができるでしょう。特に、地域社会と国際市場を結びつける政策的な枠組みが形成されることで、安定した飼養体系が構築されることが期待されます。リトアニアの地理的特性と農業の強みを活かしつつ、持続可能な将来を目指す取り組みが今後の鍵となります。
リトアニアの統計データ
- リトアニアの総人口推移【1950年~2100年】
- リトアニアの平均寿命推移【1950年~2100年】
- リトアニアの平均年齢推移【1950年~2100年】
- リトアニアの人口増加推移【1950年~2100年】
- リトアニアの鶏卵生産量の推移
- リトアニアの馬肉生産量の推移
- リトアニアの米生産量の推移
- リトアニアのトウモロコシ生産量の推移
- リトアニアの小麦生産量の推移
- リトアニアの大豆生産量の推移
- リトアニアのジャガイモ生産量の推移
- リトアニアの天然蜂蜜生産量の推移
- リトアニアのテンサイ(甜菜)生産量の推移
- リトアニアのアーモンド生産量の推移
- リトアニアのクルミ(胡桃)生産量の推移
- リトアニアのオリーブ生産量の推移
- リトアニアのキャベツ生産量の推移
- リトアニアのほうれん草生産量の推移
- リトアニアのトマト生産量の推移
- リトアニアのカリフラワー・ブロッコリー生産量の推移
- リトアニアのカボチャ・スクワッシュ・ヒョウタン生産量の推移
- リトアニアのキュウリ類生産量の推移
- リトアニアのナス生産量の推移
- リトアニアのニンニク生産量の推移
- リトアニアのネギ生産量の推移
- リトアニアの牛乳生産量の推移
- リトアニアのエンドウ豆(生)生産量の推移
- リトアニアのニンジン・カブ類生産量の推移
- リトアニアの大麦生産量の推移
- リトアニアのキノコ・トリュフ生産量の推移
- リトアニアのバナナ生産量の推移
- リトアニアのオレンジ生産量の推移
- リトアニアのレモン・ライム生産量の推移
- リトアニアのリンゴ生産量の推移
- リトアニアのナシ生産量の推移
- リトアニアのサワーチェリー生産量の推移
- リトアニアのさくらんぼ生産量の推移
- リトアニアの桃(モモ)・ネクタリン生産量の推移
- リトアニアのイチゴ生産量の推移
- リトアニアのラズベリー生産量の推移
- リトアニアのブルーベリー生産量の推移
- リトアニアの豚飼育数の推移
- リトアニアの鶏飼養数の推移
- リトアニアのヤギ飼養頭数の推移
- リトアニアの牛飼養数の推移
- リトアニアの馬飼養数の推移
- リトアニアのブドウ生産量の推移
- リトアニアのスイカ生産量の推移
- リトアニアのメロン生産量の推移
- リトアニアのアボカド生産量の推移
- リトアニアのキウイフルーツ生産量の推移
- リトアニアのオート麦生産量の推移
- リトアニアの牛乳生産量の推移
- リトアニアのそば生産量の推移
- リトアニアのヨーグルト生産量の推移
- リトアニアの羊飼養数の推移
- リトアニアの羊肉生産量の推移
- リトアニアのヤギ肉生産量の推移
- リトアニアの羊の毛生産量の推移
- リトアニアのアスパラガス生産量の推移
- リトアニアのレタスおよびチコリ生産量の推移
- リトアニアのプラムとスロー生産量の推移
- リトアニアのイチジク生産量の推移